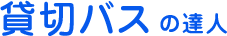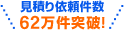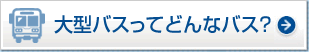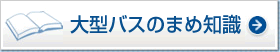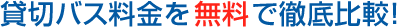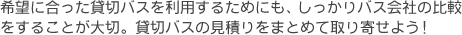大型バスの歴史
バスの始まり
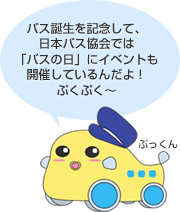
明治26年9月20日、京都にて乗合の自動車運行が始まりました。この日は、バスが一番初めに走った「バスの日」として今でも親しまれています。
当時はライバルであった乗合馬車屋などからの妨害や、車両の故障などで安全面に置いて不安を持たれることが多くありました。
しかし、大正時代に入れば自動車の信頼性も高まり全国的にバス事業の大きく成長する時期となります。
大正12年の関東大震災の際、路面電車が大きな被害を受けた時の応急処置として、約800台のバスが導入され、移動手段として大変重宝されました。
2011年3月11日の大災害でもバスは他の交通機関が機能しない緊急事態に欠かせない交通手段の一つです。
バスの大型化

昭和に入って、バス事業はさらに勢いを増していきました。事業同士の合併や統合を繰り返しながら、市域の重要な交通手段としてさらに発展していきます
しかし太平洋戦争ではバスの需要はありながら燃料の不足などから運行が難しく、最終的には軍用のトラックを事業用のバスに改造し、使用していたバス会社もありました。
そして戦後、輸送需要拡大を迎えて、バス業界は国産ディーゼルバスの普及とその大型化が進んで行きました。
昭和26年には、大阪市で日本初のワンマンカーが登場しました。都市の拡大に伴い、運行時間が延長され、昭和30年代、オリンピック開催や、東海道新幹線の開通などで、社会背景もバス業界も盛況を迎えます。
バスの需要が増え、バス事業の系列化や大手私鉄の地方進出によって、バスターミナルのプラットフォームを構築。地方都市に行っても必ずバスがあるという状況を迎えることとなりました。
長距離バスの誕生

昭和30年代の需要拡大によるバスの大型化や、大手私鉄の地方進出に伴い、都市間の長距離輸送にバスが利用されるようになります。同時に外国人向けの貸切バスの需要も増えてきました。
昭和44年に全線開通した東名高速道路にも長距離バスが走るようになりました。この時に電気バスの導入やバス優先レーンの設置、バスの位置情報を把握するバスロケーションの運用など様々な取り組みが始まっています。
平成15年に日本のバス事業は100周年を迎えました。貸切バスや路線バスを始めとするバス事業は、これからも都市間をつなぎ、地域の公共交通機関としてさらなる進展をしていくことでしょう。