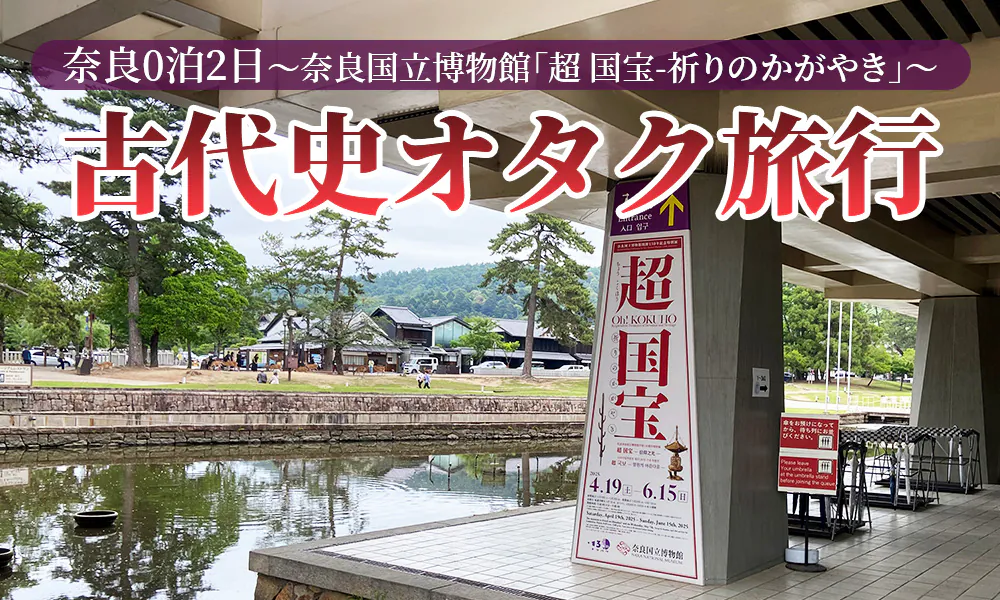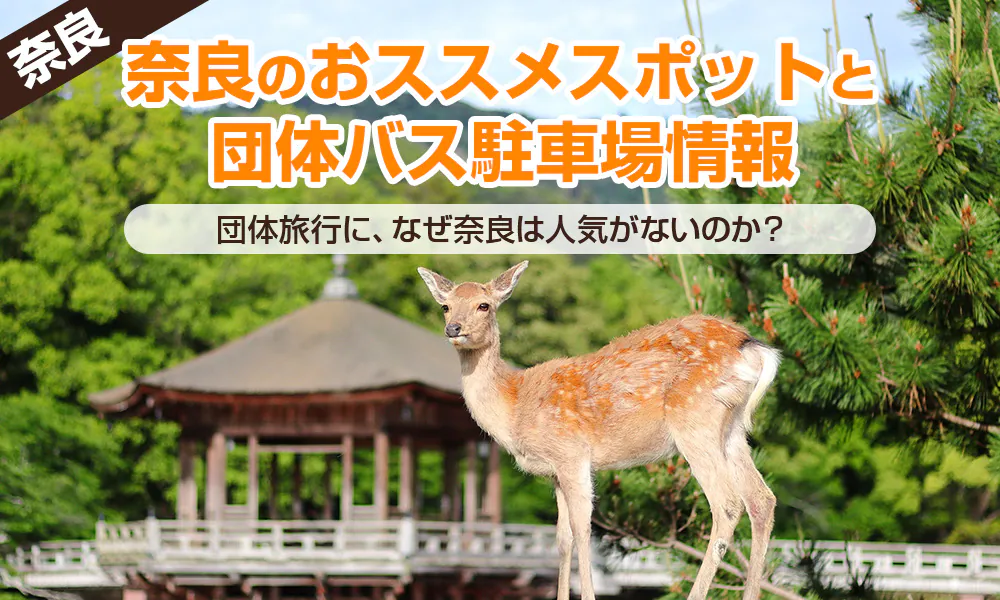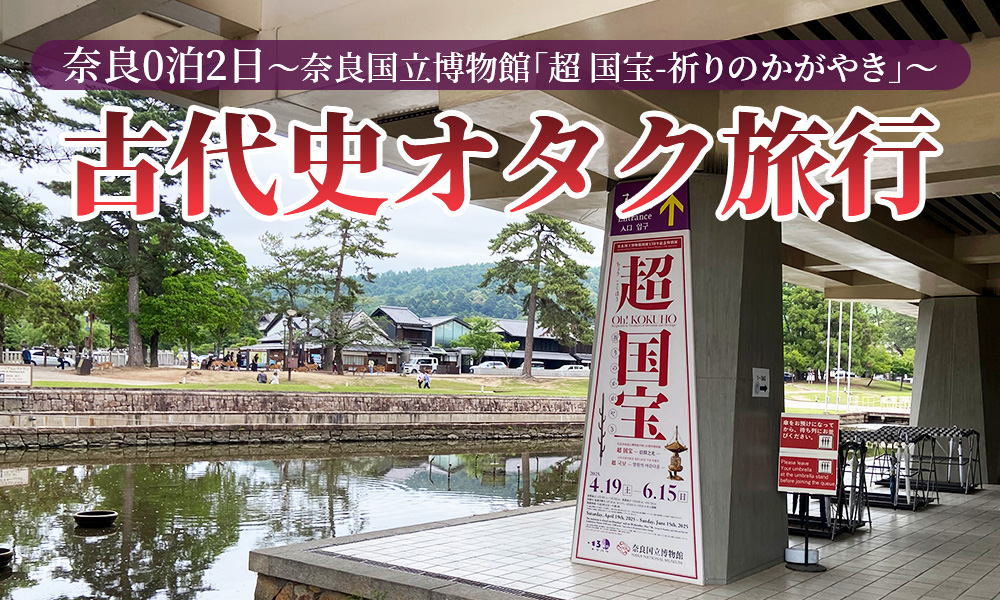古都・奈良の秋を彩る行事「鹿の角きり」。奈良で人気の紅葉スポットも大特集
「鹿の角きり」は、江戸時代初期、寛文11年(1671年)から今日まで、350年以上にわたり、受け継がれている古都・奈良の伝統行事です。
発情期をむかえた雄鹿の角により、町民が危害を受けたり、鹿がお互いに突き合って死傷することを防ぐために始まったといわれています。
当時は、町の所々で行われ、店先や人家の格子の中、屋根の上などから見物していたそう。奈良町の杉の丸太で造られた太くて丈夫な格子は『鹿格子』または『奈良格子』と呼ばれているのは、ここからきているとか……。
昭和4年に春日大社境内に「鹿苑」が完成し、その一部に角きり場が設けられ、年中行事として開催されるようになっています。
はちまきに、はっぴ姿の勢子(せこ)たちが、鹿を3~4頭を角きり場に追い込みます。捕獲道具である「十字」や「だんぴ」などを使い、荒々しく走りまわる鹿の角に縄をかけ、これをたぐりよせ、あばれる鹿を捕りおさえます。
烏帽子、直垂姿の神官が、鹿の気を静めるため水を含ませ、のこぎりで慎重に角を切り、神前に供えます。角を切られた鹿は、奈良公園に戻されます。

古都奈良ならではの勇壮な伝統行事を、ぜひ間近で見てみませんか。イベントの収益は「奈良の鹿」保護活動に活用されます。
2025年は例年10月に行ってきましたが、2025年は11月に行うそうなのでご注意くださいね。
Information
鹿の角きり行事
【開催日時】2025年11月8日(土)・9日(日)
11時45分~15時(開場11時15分、最終入場14時30分まで)
【開催場所】春日大社境内 鹿苑(ろくえん)角きり場(奈良公園内)
【観覧料金】大人(中学生以上)1,000円・小人(小学生)500円
※愛護会会員・同伴者1名まで無料
●小雨決行・荒天中止
●完全入れ替え制、全て立見席
●場内バリアフリーではありません
●ペット同伴での入場不可
●三脚の使用は禁止
【問合せ先】0742-22-2388 一般財団法人 奈良の鹿愛護会
編集部が気になった奈良県・紅葉の名所5選+ススキの名所
奈良の紅葉は10月下旬~12月上旬にかけて見頃を迎えます。関西で紅葉というと京都ばかりがクローズアップされがちですが、奈良も魅力的な紅葉スポットがたくさん。
おススメをピックアップしてみました。
お花のお寺として有名な長谷寺は紅葉も見事

桜井市にある真言宗豊山派の総本山・長谷寺は四季折々に美しい花が咲くことから「花の御寺」として有名です。山の斜面に建つ本堂の外舞台から見渡す紅葉はそれはそれは見事。
礼堂の磨かれた床板に赤・黄色に色づいた紅葉が写り込む「床もみじ」はSNS映えすると大人気に。賓頭盧尊者像(びんずるそんじゃぞう)のシルエットと共に撮影するのが定番となっています。
ご本尊である十一面観世音菩薩立像の特別拝観は2025年10月4日~12月7日まで。普段は触れることができないご本尊のおみ足に触れることができる特別な機会となっています。
どうぞお見逃しなく!
Information
長谷寺
入山時間:10月~11月・3月 9時~17時/12月~2月 9時~16時30分/4月~9月 8時30分~17時
入山料金:大人(中高生含む)500円、小学生250円
※30名以上の団体で割引あり
住所:奈良県桜井市初瀬731-1
問合せ先:0744-47-7001
観光バス駐車場:あり、2,000円
写真家・土門拳さんを魅了した室生寺の紅葉

長谷寺、岡寺、壷阪寺とともに「大和観音もみじ回廊」が行われる室生寺。11月1日から土日祝にライトアップも行われます。
国宝である金堂や五重塔などの堂塔とモミジ、イチョウなどのコラボレーションは素晴らしく、特に太鼓橋から本堂までの参道が見どころの1つ。
Information
室生寺
拝観時間:8時30分~17時
入山料:大人600円、子ども400円
住所:奈良県宇陀市室生78
問合せ先:0745-93-2003
観光バス駐車場:室生寺前さかや駐車場 1,500円(マイクロバス1,000円)、おもや駐車場 1,600円(マイクロバス1,200円)、タイムズ室生寺(奈良県宇陀市室生1325)4台分、2,000円~
桜の名所は紅葉の名所でもある吉野山の紅葉

大峰連山北端約8kmにわたる尾根で桜の名所として有名な吉野山。主に桜ともみじの紅葉が美しいことで知られています。
萌えるような赤・黄色・だいだい色に染まる秋の吉野山も魅力的。10月中旬からじょじょに色づきはじめるので、24日(金)~11月30日(日)まではライトアップも行われます。
2025年10月24日(金)~11月30日(日)は世界遺産・金峯山寺蔵王堂(国宝)の秘仏・ご本尊を特別に御開帳。この他普段は拝めない仏像や宝物の特別拝観もあるのでぜひ合わせて巡りましょう。
Information
吉野山
住所:奈良県吉野郡吉野町吉野山
問合せ先:0746-32-1007(吉野山観光協会)
観光バス駐車場:吉野山観光駐車場(大型バスも可)/如意輪寺前駐車場 11,000円~
※観桜期間中は完全予約制(0746-32-2036 バス駐車場予約センター)
おすすめコースはこちら≫
奈良市内の穴場スポット、国指定名勝「依水園」

奈良市内の中心にあり、東大寺と興福寺の間にありながら静かな環境にある穴場の庭園。11月中旬~下旬頃にドウダンツツジ、イロハモミジ、ハゼの紅葉、センダンの黄葉が美しく庭園を彩ります。
江戸と明治と異なる時代で作られた2つの池泉回遊式庭園で、東大寺南大門、若草山、春日山などを借景として四季折々の美しさを楽しめます。
東大寺・奈良国立博物館などとともに周遊してみてはいかがでしょうか。
Information
依水園
開園時間:9時30分~16時30分(入園は16時まで)、毎週火曜、庭園整備期間休み
入園料:1,200円、大高校生500円、小中学生300円
※15名以上の団体で割引あり
住所:奈良市水門町74 依水園
問合せ先:0742-25-0781
↓観光バス駐車場は以下の記事を参考に
天川村「みたらい渓谷」は山一面が秋色に染まります

巨石・奇石、大小の滝と豊富な種類の木々がつくる大自然の景観など、見どころがいっぱいのみたらい渓谷。紅葉シーズンの土・日・祝日は大変混雑することで有名なので、平日を狙って訪れてみましょう。
近くには洞川温泉、天の川温泉もあります。
Information
みたらい渓谷
住所:吉野郡天川村北角
問合せ先:0747-63-0999 (天川村総合案内所)
観光バス駐車場:事前に要問合せ
葛城高原と曽爾高原のススキ

御所市にある標高960mの葛城山は、春にツツジの名所として知られていますが、秋は一面ススキ野原となり、黄金色に輝く枯れススキの見ごろは10月以降に訪れます。
山頂へは葛城ロープウェイが結んでおり、気軽にアクセス可能です。
もう一か所のススキの名所は曽爾(そに)高原。宇陀郡曽爾村にあり、倶留尊山(標高1038m)と亀の背に似た亀山(標高849m)を結ぶ西麓に広がっています。
10月上旬になると辺り一面ススキで覆われ、11月下旬には金色に染まります。

曾爾高原ではススキの見ごろに合わせて「曾爾高原山灯り」を2025年11月24日(月)まで開催。お亀池周辺では、日没より200個の灯籠が飾られとても幻想的です。
曽爾高原の夕景から幻想的な山灯り、そして満点の星空を楽しんでみては?
Information
葛城高原
住所:奈良県御所市櫛羅
問合せ先:0745-62-5083 (葛城高原ロッジ)
観光バス駐車場:あり。大型・中型バス5,000円、マイクロバス2,500円
曾爾高原
住所:奈良県宇陀郡曽爾村太良路
問合せ先:0745-94-2106 (曽爾村企画課)
観光バス駐車場:あり。利用日の1週間前までに要予約、当面無料
バス専用駐車場予約窓口:0745-94-2022(一般社団法人そにのわGLOCAL 平日9時~17時)
「ライトアッププロムナード・なら」通年で開催中

奈良公園周辺に点在する東大寺等の歴史的建造物、計9箇所をライトアップし、奈良の夜を演出。夜の散策も楽しませてくれています。
ライトアップスポット
猿沢池 〔通年点灯施設〕
池に映る月は奈良八景のひとつとして有名。毎年、中秋の名月の日には池の北西にある采女神社で采女祭が催されます。
興福寺・五重塔 〔当面休止〕
世界遺産に登録された文化財のひとつ。深い松の緑の中から夜空に向かってそびえ立つ荘重な姿が印象的
春日大社 一の鳥居 〔通年点灯施設〕
836年の造営と伝えられている重要文化財。春日鳥居の典型といわれています。
夜景に映える朱色の美しさが印象的。
奈良国立博物館なら仏像館(本館) 〔通年点灯施設〕
フレンチ・ルネッサンス風の建物は、明治28年に完成し、重要文化財に指定。夕闇の中にたたずむ姿に古き良き時代が忍ばれます。
浮見堂 〔通年点灯施設〕
奈良公園内の鷺池に建つ六角形の建物。水面に映る姿はとても美しく、映えスポットとして人気です。
仏教美術資料研究センター 〔通年点灯施設〕
明治35年、当時奈良県の古社寺修理技師であった関野貞(せきのただし)の設計により完成。平成23年7月に、ライトアップ施設をリニューアル。
東大寺(大仏殿、中門、南大門) 〔期間限定〕
奈良のシンボルともいえるお寺で、こちらも平成10年末に世界遺産に登録。 東大寺の大仏殿は世界最大の木造建築物です。中門は回廊とともに重要文化財。
平城宮跡・朱雀門 〔通年点灯施設〕
世界遺産・平城宮跡の入口となる巨大な門は平成10年に復原されたもの。併せて、平城遷都1300年を記念して復原された第一次大極殿もライトアップ。
第一次太極殿(平城宮跡) 〔通年点灯施設〕
平城遷都1300年を記念して復元された宮殿。外国からの来賓や天皇の即位式など重要な儀式の舞台となりました。
薬師寺 〔通年点灯施設〕
天平時代の姿をそのままに今に伝える東塔、昭和に再建された西塔と金堂、3つの建物が眩い光に包まれ、西の京の夜空に幻想的な空気が漂います。
Information
ライトアッププロムナード・なら
ライトアップ時間は19時~22時(9月は18時~22時)
墨の製造工程見学・にぎり墨の体験

奈良では古来より、品質の良い墨がつくられる場所として歴史にその名が刻まれてきました。しかしながら、安政の大地震、黒船の来航等幕末の内憂外患によって、奈良の産業は潰滅的になり、明治元年には11軒の墨屋しか残らぬ状況で明治維新を迎えることになります。

墨は炭素末(たんそまつ)(煤=すす)と膠(にかわ)と少しの香料をねり合せてできています。
墨の起源は約3500年前、中国の殷の時代(紀元前1500年頃)。漢の時代に入り、105年に蔡倫(さいりん)が紙を発明し、これに伴ない墨の需要が急速に高まり、現在ある墨の原形となるものが生れ、唐の時代(618~907年)には今日の墨の形が整えられたといわれています。
この頃には日本との交流は盛んになり、当時の墨が日本に伝来し、正倉院に今もなお宝蔵されています。
宋の時代の中国では原料である「すす=煤」を植物油を燃やして採っており、この墨を油煙墨(ゆえんぼく)と言いますが、唐墨(からすみ)と称して日本では貴族達が珍重していました。一方、日本の墨と言えば、まだ松を燃やして「すす」を採る(松煙墨)古来ながらの製法で、品質的にもいまひとつ。
平安時代には、各地でつくられていた墨も時代の変遷と共に次第に途絶えて行く中、奈良の墨は、寺社を中心としてつくり続けられました。南都(奈良)の墨=油煙墨として、これまで作られていた松煙墨とは、墨の色、艶、磨(す)り心地など品質的に圧倒的な優位に立ち、全国に知られるようになったそうです。
興福寺ニ諦坊でつくられていた墨の墨型(銅製)は今もなお残されています。
そんな歴史的いきさつから、奈良では墨の工場見学やにぎり墨体験ができる場所があります。最近では、お習字で墨をすることも少なくなっています。この機会にぜひ、古都の歴史の一端に触れてみてはいかがでしょうか?
にぎり墨体験可能な施設
錦光園 工房見学・にぎり墨体験
・所要時間:40~60分
・対応時間:9時~19時
・工房では35名迄、それ以上は出張体験可。
・体験料2,200円(高校生以下は1,650円) ※要予約
問合せ先:0742-22-3319 錦光園
古梅園 *にぎり墨体験は11月~4月中旬まで
・所要時間:30~40分
・対応時間:10時30分~14時頃 ※土・日曜・祝日休、年末年始
・受入人数は~25名まで
・体験料:4,000円~ ※墨の種類により異なる
問合せ先:0742-23-2965 古梅園
墨の資料館(がんこ一徹長屋併設) *にぎり墨体験は日曜を除く10月~4月
・所要時間:10分~30分(人数による)
・対応時間:10時~14時30分
・受入人数は1回につき~30名程度
・体験料:1名1,650円(学生は1,100円) ※要予約
問合せ先:0742-41-7011
※料金やサービス等は取材当時のものです。最新の情報は公式ホームページを参照してください。
バス会社の比較がポイント!